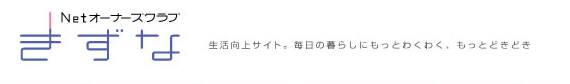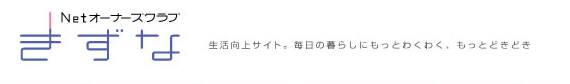|
平松さんが食べることに興味を持った最初は何ですか?
やはり母がつくってくれた料理でしょうね。母の料理は手を抜かない料理。お味噌汁ひとつとってもおいしかった。当時はまだ珍しい焼き立てのパンを買いに、朝パン屋さんに行っていました。「あれ?おかあさんどこに行ったのかな」と思っていると、母が帰って来る。「ありがたいなー」と思っていました。生まれたのは岡山県の倉敷で、祭り寿司が有名ですが、10種類以上の具をそれぞれに味つけてつくっていました。口に入れるとそれぞれの食感が重なるようにふわぁ〜っと広がっていく、とても贅沢な味だと思いましたね。私は前の日に母がかんぴょうを水で戻したり、しいたけをゆっくりゆっくり煮ていた・・そんなことを思い返しながら味わっていました。進学のために上京して自分で食事をつくることになって、それがいかに貴重なことだったかを実感するのですが。
社会を見るフィルターとしてなぜ「食」を選んだのですか?
大学では社会学を専攻して調査など方法論を勉強したのですが、正直、机の上での理論は実感がわきませんでした。でも社会に出て、結婚してから、日々食と向き合うようになり、食は家庭内だけのものではなく、農業問題など社会のさまざまな面とつながっている広がりのあるテーマだとわかったのです。在学中から書く仕事はしていたのですが、こうした実体験を通して、テーマを絞って「食」について書こうと思いました。
最初はどんなテーマで取材をしたのですか。
在日外国人の方が日本でどんな食生活を送っているのかに興味を持って、取材しました。取材に伺ったのはアジアやヨーロッパなどから来た方々のお宅です。小さなアパートのキッチンから豪邸のキッチンまで。母国の料理が日本という外国でどんなふうに変化していくのかフィールドワークをしました。材料が揃わないでしょう?みんな日本にある似たもので代用している。でも、誰もが「ここだけは譲れない」という物を持っているんですね。たとえばネパールやインドの方は必ずスパイスを入れる箱を持っていたし、タイの家庭には必ず「石臼」がありました。個人の事情が食に反映していることも発見しました。キッチンって不思議な場所ですね。そこでは、あらたまったインタビューの場では出ない話がぽろぽろと出てくるんですから。
それで、本国に行こうと? さまざまな国を訪ねています。特に韓国は繰り返し訪ねていますね。
私はヨーロッパも大好きだし、各国を訪れていますが一番体調がいいのが韓国に行った時なんですね。最初に行ったのが1982年。軍事政権下でした。日本人にとっても韓国は遠い国という感じで、今の「韓流ブーム」なんて夢のよう。貧しい中でもヤンニョムなど調味料は家庭で手づくりが基本。韓国料理というのは「手の味」なんですね。素材と調味料を混ぜ合わせ、沁み込ませるのに使うのは主に手。手で混ぜないとしっかり味が素材に入っていかないし、指の動きを変えて味つけを変えていくこともあります。そのキメ細やかさにいつも感銘を受けるんです。それでも、何度も行っているので、少し前にふと、「韓国の味のほとんどはわかったかな」と思った時期がありました。でも、それは大きな間違いで(笑)、そんな時ほど、これまで私が知っているのは韓国料理のごくわずかじゃないかと思わせるような食べ物に巡り合ったりするんです。今でも韓国への取材旅行は3泊4日で2カ所を訪ねるといった短い日程。車で山の奥まで行きますが、どんな食べ物に出会えるのか、興味は尽きないですね。日本もそうですが、今残さなくては消えてしまう食文化を、書くことでなんとかして残したいという思いがあります。そう言うと時々、韓国の人に「日本人のあなたが?」って不思議そうな顔をされます(笑)。
平松さん自身の今の食生活はいかがですか?
わが家は朝食中心ですね。私は明け方から仕事をするのですが、一段落すると、「さあ、朝ご飯だ」って張り切って5〜6品つくって家族でいただきます。肉料理もあるので、うちの朝食は晩ご飯のようにボリュームたっぷり。反対に夜は簡単にしています。料理をつくるのは仕上がりをイメージしながら、1つ1つの素材や味付けが全体の中でどういう位置づけになるかを考えて手を動かしていく作業。その手間や知恵を大事にしたいですね。
食に関してはまだまだ書きたいことがたくさんあります。長く書いていますが、書くテーマには困りません。「食」をフィルターにして暮らしや文化を見ていくことは私にとって、尽きることのないテーマだと思います。 |